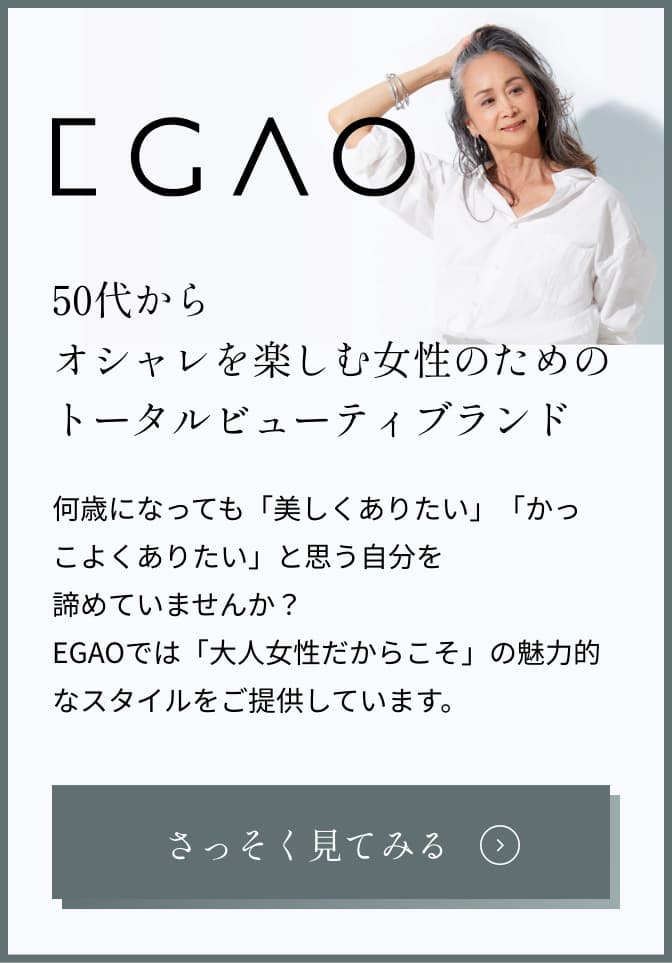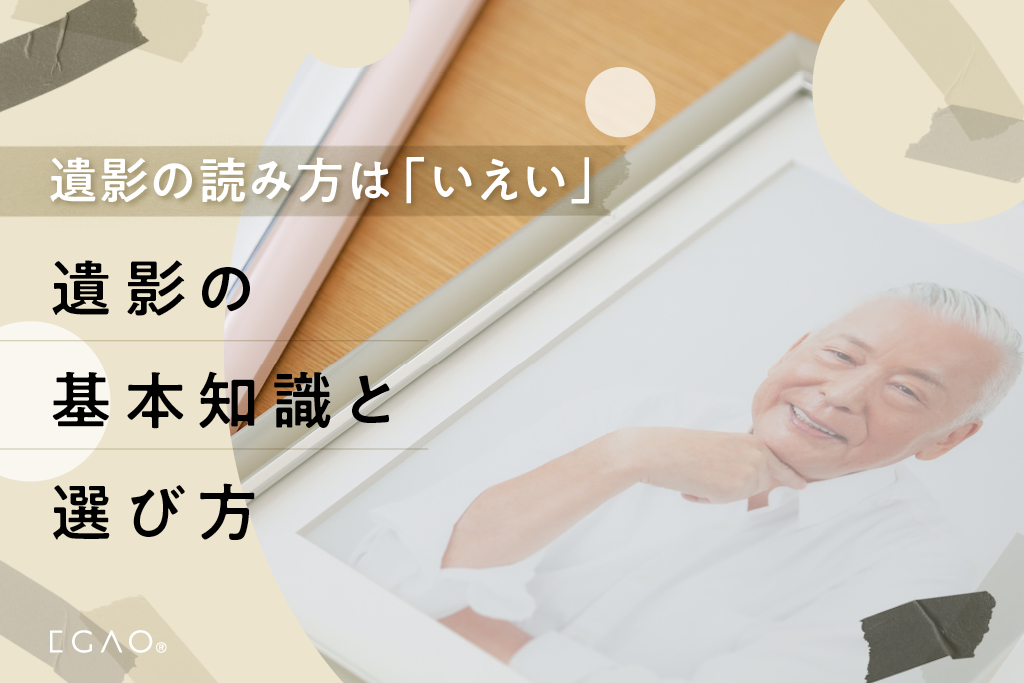ステキなヒント
遺影を飾るのがよくない噂は本当?写真館が解説する正しい知識
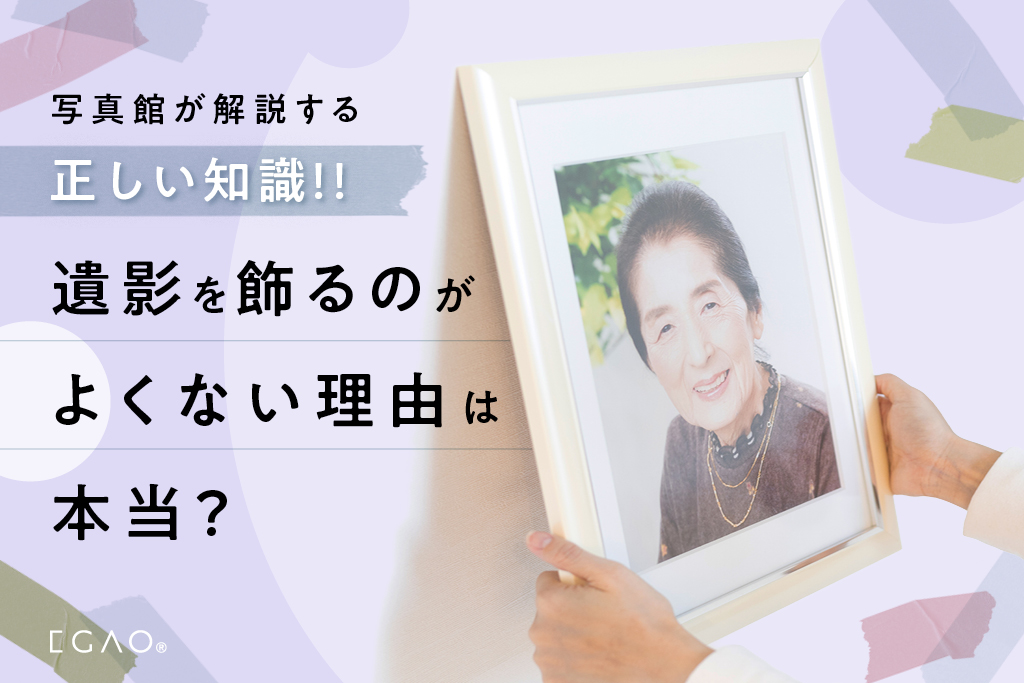
- 1. 「遺影を飾るのがよくない」と言われる3つの理由
- 1.1. 理由1. 風水的によくないという迷信について
- 1.2. 理由2. 宗教的な意味での誤解について
- 1.3. 理由3. 実用的な問題(湿気・日光など)について
- 2. 写真館のプロが教える遺影の正しい基礎知識
- 2.1. 遺影の本来の意味と目的
- 2.2. 遺影に宗教的意味はない事実
- 2.3. 現代における遺影の役割の変化
- 3. 遺影を飾りたくない気持ちは自然な感情です
- 3.1. 住宅事情による現実的な問題
- 3.2. 心理的な負担を感じる理由
- 3.3. 代替案という選択肢があること
- 4. 遺影を飾る場合に本当に避けるべき場所とは
- 4.1. 実用的に避けるべき場所(湿気・直射日光・火気)
- 4.2. 宗教的配慮が必要な場所(仏壇の上など)
- 4.3. おすすめの飾り方と場所の提案
- 5. 遺影を飾らない選択肢と現代的な供養方法
- 5.1. 小さくリサイズして保管する方法
- 5.2. デジタル化による新しい形の供養
- 5.3. 一時的な保管という選択肢
- 6. 写真館に寄せられるよくある質問と回答
- 7. まとめ
遺影専門写真館で15年間働いている私のもとには、日々多くのご遺族からさまざまなご相談が寄せられます。その中でも特に多いのが「遺影を飾るのはよくないと聞いたのですが、本当でしょうか?」というお悩みです。
結論から申し上げますと、遺影を飾ることに問題は一切ありません。むしろ、故人を偲び、大切な思い出を身近に感じるための素晴らしい方法の一つです。
しかし、なぜこのような迷信が生まれ、多くの方を不安にさせているのでしょうか。写真館での豊富な経験をもとに、遺影に関する正しい知識をお伝えいたします。
「遺影を飾るのがよくない」と言われる3つの理由

理由1. 風水的によくないという迷信について
お客様からよく「風水で遺影を飾るのはよくないと聞きました」というご相談をいただきます。確かに、インターネット上には「玄関に遺影を飾ると運気が下がる」「写真に悪いエネルギーが宿る」といった情報が散見されます。
しかし、これらは科学的根拠のない迷信です。
風水の本来の考え方は、住環境を整えることで生活の質を向上させることにあります。遺影そのものが運気に悪影響を与えるという考えは、風水の本質とは異なります。
実際に写真館で働いていて感じるのは、遺影を大切に飾られているご家庭ほど、故人への感謝の気持ちを忘れず、家族の絆も深いということです。これこそが真の「良い気」の流れと言えるのではないでしょうか。
ただし、風水を気にされる方でも安心して遺影を飾れるよう、以下の点にご注意いただければと思います。
- 玄関の正面は避ける: 来客時の印象を考慮した配慮
- 水回りは避ける: 湿気による写真の劣化防止
- 直射日光は避ける: 色褪せ防止のため
これらは風水というより、写真を良い状態で保管するための実用的なアドバイスです。
理由2. 宗教的な意味での誤解について
「遺影には魂が宿るから扱いに注意が必要」「仏壇の近くに飾ってはいけない」といった宗教的な誤解も多く聞かれます。
遺影に宗教的な意味は一切ありません。 これは仏教、神道、キリスト教のいずれにおいても共通しています。
私たち写真館では、さまざまな宗派のお客様とお付き合いがありますが、どの宗教においても遺影は「故人を偲ぶための写真」以上でも以下でもありません。位牌や仏像のような宗教的な意味を持つものとは全く異なります。
実際、遺影を飾る習慣が始まったのは明治時代以降で、日本の伝統的な仏教文化よりもはるかに新しいものです。それまでの長い間、仏教では遺影なしで供養が行われてきたのです。
ただし、宗教的な配慮として以下の点は守った方が良いでしょう。
- 仏壇の中には置かない: 仏壇は仏様の世界を表す神聖な場所
- 仏壇の真上は避ける: ご本尊を見下ろす形になるため
- 十字架がある場合はその下に: キリスト教ご家庭での配慮
これらは宗教的な「禁止」ではなく、信仰への敬意を示すマナーです。
理由3. 実用的な問題(湿気・日光など)について
「遺影を飾るのがよくない」と言われる理由の中で、唯一現実的な根拠があるのがこの実用的な問題です。
写真館のプロとして、遺影を長期間美しく保つためには以下の環境は確実に避けるべきです。
絶対に避けるべき場所:
- 高温多湿な場所: カビの発生や写真の変色の原因
- 直射日光が当たる場所: 色褪せや劣化が急速に進む
- 火気の近く: 安全面での配慮
- 振動の多い場所: 額縁の破損リスク
これらの問題は「よくない」のではなく、写真の保存という観点から「適切でない」ということです。大切な遺影を長く美しく保つための、実用的な配慮なのです。
写真館では、お客様に遺影をお渡しする際、必ずこれらの保管上の注意点をお伝えしています。正しい場所に飾れば、遺影は数十年にわたって美しい状態を保つことができます。
写真館のプロが教える遺影の正しい基礎知識
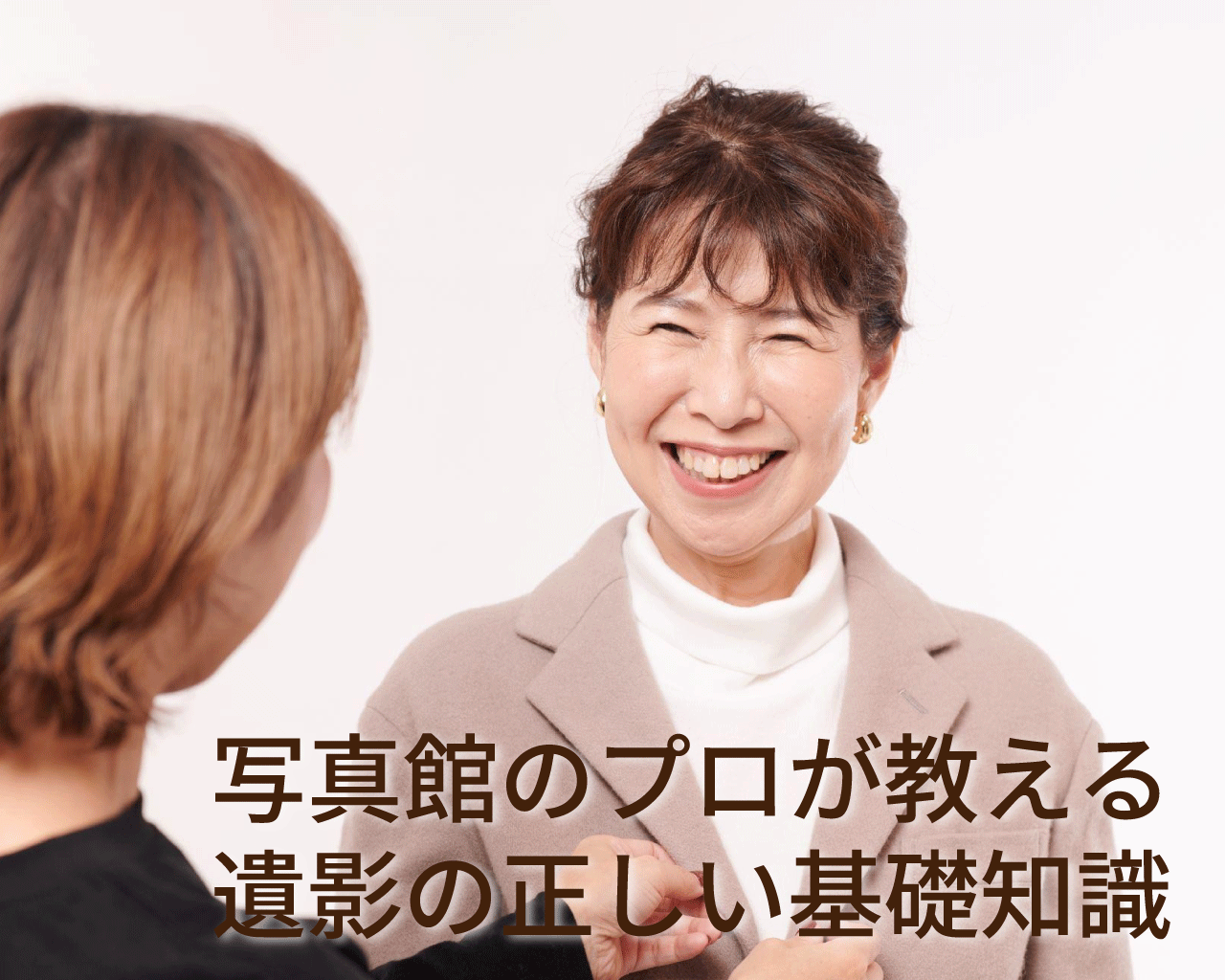
遺影の本来の意味と目的
15年間、数千人のお客様とお話しさせていただいて分かったことは、遺影の最も大切な役割は「故人との心のつながりを保つこと」だということです。
遺影の本来の目的は以下の通りです。
- 故人を偲ぶためのツール 葬儀の際、参列者が故人の生前の姿を思い出し、最後のお別れをするための手助けとなります。写真を見ることで、故人との思い出が蘇り、感謝の気持ちを伝えやすくなります。
- 家族の心の支えとして 大切な人を失った悲しみの中で、遺影は故人がまだ身近にいるような安心感を与えてくれます。多くのご遺族が「写真に話しかけることで気持ちが楽になる」とおっしゃいます。
- 世代を超えた記録として 時が経つにつれ、遺影は家族の歴史を物語る大切な記録となります。孫やひ孫の世代にとって、先祖の顔を知る貴重な資料でもあります。
遺影に宗教的意味はない事実
写真館で働いていると、「遺影には魂が宿るのでしょうか?」というご質問をよくいただきます。
遺影は写真であり、宗教的な意味は持ちません。 これは重要なポイントです。
仏教における供養の対象は位牌であり、遺影ではありません。位牌は故人の戒名が記され、仏教的な意味を持ちますが、遺影は生前の姿を記録した写真に過ぎません。
実際、江戸時代以前には遺影という概念自体が存在しませんでした。それでも先祖供養は適切に行われていたのです。
この事実を理解していただくことで、遺影に対する過度な心配や迷信から解放され、純粋に故人を偲ぶツールとして活用していただけると思います。
現代における遺影の役割の変化
現代の遺影は、従来の「葬儀で使用する厳粛な写真」から大きく変化しています。
現代の遺影の特徴:
- カラー写真が主流
- 笑顔の写真も一般的
- 背景や服装の加工技術向上
- サイズの多様化(L版からA3まで)
- デジタル化による新しい活用法
写真館でも、お客様のニーズに合わせて様々なスタイルの遺影を作成しています。「故人らしさを大切にしたい」「明るい雰囲気にしたい」といったご要望が増えており、遺影も時代とともに進化しているのです。
遺影を飾りたくない気持ちは自然な感情です
住宅事情による現実的な問題
お客様から「遺影を飾りたいのですが、マンションで狭くて…」というご相談を頻繁にいただきます。これは現代社会の現実的な問題です。
現代住宅の特徴:
- 仏間や床の間がない住宅の増加
- コンパクトな間取り
- 洋風インテリアとの調和の問題
- 賃貸住宅での制約
これらの問題は「遺影を飾りたくない」理由として完全に正当なものです。無理をして飾る必要はありません。
写真館では、こうした現代の住宅事情に合わせて、様々なサイズの遺影をご提案しています。従来の四つ切りサイズ(254mm×305mm)だけでなく、L版(89mm×127mm)や2L版(127mm×178mm)など、小さめのサイズも人気です。
心理的な負担を感じる理由
「遺影を見るのがつらい」「悲しみが蘇ってしまう」といった心理的な理由で飾りたくない方もいらっしゃいます。
これは自然で健全な感情です。グリーフ(悲嘆)の過程では、故人を思い出すものを一時的に遠ざけたくなることがあります。
心理学的にも、悲しみの処理には個人差があり、遺影を飾ることが必ずしも癒しにつながるとは限りません。無理に飾る必要はなく、ご自身の心の状態に合わせて判断していただくのが最良です。
写真館では、そのようなお客様には以下のようなアドバイスをしています。
- 一時的な保管: 気持ちの整理がつくまで大切に保管
- 小さなサイズで作成: 負担の少ないサイズから始める
- デジタル保存: 物理的な写真ではなくデータとして保管
代替案という選択肢があること
遺影を従来の形で飾らなくても、故人を偲ぶ方法は数多くあります。
現代的な供養・記念の方法:
デジタルフォトフレーム
複数の写真をスライドショーで表示できるため、様々な表情の故人を見ることができます。明るい思い出の写真も含められるため、悲しみよりも良い思い出を重視したい方におすすめです。
小さなフォトスタンド
リビングの棚やサイドボードに置ける小さなフォトスタンドなら、インテリアにも馴染みやすく、日常的に故人を身近に感じられます。
アルバム形式
一冊のアルバムに故人の写真をまとめ、見たいときに開くという方法もあります。写真館でも、遺影用の写真と一緒に思い出の写真をアルバムにまとめるサービスを提供しています。
遺影を飾る場合に本当に避けるべき場所とは
実用的に避けるべき場所(湿気・直射日光・火気)
写真館のプロとして、遺影を長期間美しく保つために絶対に避けていただきたい場所をお伝えします。
湿気の多い場所
- 浴室近く: 湿度が高くカビの原因となる
- 洗面所: 水蒸気による影響
- 台所: 油煙と湿気の両方の影響
- 外壁に面した北側の壁: 結露しやすい場所
実際に写真館にお持ち込みいただく遺影の中には、カビが発生してしまったものもあります。一度カビが発生すると完全な除去は困難で、写真の価値が大きく損なわれてしまいます。
直射日光が当たる場所
- 南向きの窓際: 最も日光の影響を受けやすい
- 西向きの窓近く: 午後の強い日差しによる影響
- スカイライト(天窓)の下: 上からの日光による劣化
写真の色褪せは不可逆的な変化です。一度色褪せしてしまった写真を元の状態に戻すことはできません。
火気の近く
- 仏壇のろうそくの近く: 火災のリスク
- ストーブやヒーターの近く: 熱による劣化
- 台所のコンロ周辺: 油煙と熱の影響
安全面での配慮はもちろん、熱による写真の劣化も深刻な問題です。
宗教的配慮が必要な場所(仏壇の上など)
宗教的な意味はないとはいえ、信仰への敬意として以下の配慮をお勧めします。
仏壇関連
- 仏壇の中: 仏様の世界に生前の姿は適さない
- 仏壇の真上: ご本尊を見下ろす形になる
- 仏壇の正面: お参りの際に背を向ける形になる
これらは「絶対にダメ」ということではなく、信仰への配慮としての提案です。
神道・キリスト教での配慮
- 神棚の上: 神様より高い位置は避ける
- 十字架の上: キリストより高い位置は避ける
それぞれの信仰に合わせた配慮をしていただければと思います。
おすすめの飾り方と場所の提案
写真館でお客様におすすめしている、理想的な遺影の飾り方をご紹介します。
最適な場所:
リビングの目線の高さ
家族が最も長く過ごす場所で、自然に故人を身近に感じられます。テレビボードの上や本棚の一角など、普段の生活に溶け込む場所がおすすめです。
廊下の壁面
家族が日常的に通る場所で、来客の目にも自然に触れます。「いつも見守ってくれている」という安心感を得やすい場所です。
寝室の枕元
プライベートな空間で、ゆっくりと故人を偲びたい方に適しています。就寝前のひとときに故人と心の対話を楽しめます。
最適な高さと角度:
- 目線の高さ: 座った時に自然に目が合う高さ
- 少し見上げる角度: 敬意を表す意味でも効果的
- 安定した場所: 地震などでも落下しにくい場所
照明の工夫: 間接照明やスポットライトを使って、遺影を美しく照らすことで、より心温まる空間を作ることができます。ただし、熱を持つ照明は避けてください。
遺影を飾らない選択肢と現代的な供養方法
小さくリサイズして保管する方法
「大きな遺影は飾れないけれど、完全になくすのは寂しい」というお客様には、リサイズをお勧めしています。
リサイズのメリット:
- 省スペース: どんな住環境でも対応可能
- 負担軽減: 心理的プレッシャーの軽減
- インテリア調和: 洋風の住宅にも馴染みやすい
- 移動容易: 引っ越しや模様替えが楽
写真館では、元の遺影からL版、2L版、はがきサイズまで様々なサイズで複製を作成できます。デジタル技術により、小さくしても画質の劣化はほとんどありません。
保管方法の提案:
- 写真立てに入れて引き出しに保管
- アルバムの表紙に貼り付け
- 手帳サイズでいつも持ち歩く
- 車のダッシュボードに小さく飾る
デジタル化による新しい形の供養
現代ならではの供養方法として、デジタル化が注目されています。
デジタル遺影の活用法:
デジタルフォトフレーム
写真館で最近人気が高まっているのがこの方法です。故人の様々な表情を時間ごとに表示でき、生前の豊かな思い出を蘇らせることができます。
メリット:
- 複数の写真を表示可能
- 音楽付きスライドショー
- リモコンで操作可能
- 場所を取らない
スマートフォン・タブレット
いつでもどこでも故人の写真を見ることができ、現代人のライフスタイルに最も適した方法かもしれません。
クラウドストレージ
家族全員で故人の写真を共有でき、離れて住む家族ともつながりを保てます。
一時的な保管という選択肢
「今はまだ飾る気持ちになれないけれど、将来は飾りたい」という方には、適切な保管方法をお教えしています。
長期保管のポイント:
- 密閉容器での保管: 湿気とほこりを防ぐ
- 防虫剤の使用: 虫食いを防ぐ(写真用の防虫剤を使用)
- 温度の安定した場所: 押し入れの上段など
- 定期的な点検: 年1回程度の状態確認
写真館では、保管用の専用ケースもご用意しており、数十年間の長期保管にも対応できます。
時間が経って心の整理がついた時に、改めて飾っていただくことができます。故人への思いに時間的な制限はありません。
写真館に寄せられるよくある質問と回答
A: 遺影を飾る期間に決まりはありません。
宗教的な儀式としては、四十九日までは後飾り祭壇に遺影を飾ることが一般的ですが、それ以降については完全に自由です。
写真館のお客様の中には:
- 永続的に飾る方: 先祖代々の遺影と一緒に飾り続ける
- 季節ごとに飾る方: お盆や命日などの特別な時期だけ飾る
- 数年で片付ける方: 心の整理がついた時点で保管に切り替える
- すぐに片付ける方: 葬儀後すぐに保管する
どの選択も正しく、間違いはありません。大切なのは、ご家族の気持ちと生活スタイルに合わせることです。
A: 法律的には一般ゴミとして処分できますが、気持ちの問題もあります。
遺影は法的には普通の写真と同じ扱いなので、各自治体のルールに従って処分できます。しかし、多くの方が心理的な抵抗を感じられます。
処分方法の選択肢:
お寺・神社での供養
菩提寺や近隣のお寺・神社に相談すると、お焚き上げをしてもらえることがあります。費用は3,000円〜10,000円程度が相場です。
葬儀社での引き取り
葬儀を依頼した葬儀社が引き取ってくれる場合があります。まずは相談してみてください。
写真館での引き取り
私たち写真館でも、作成した遺影の引き取りサービスを行っています。適切な方法で処分いたします。
自分で処分する場合
どうしても自分で処分する場合は、感謝の気持ちを込めて、きれいな紙に包んでから処分することをお勧めします。
A: コミュニケーションを重視し、全員が納得できる折衷案を見つけましょう。
写真館では、このようなご相談を頻繁にいただきます。特に多いのが以下のようなケースです:
よくある対立パターン:
- 高齢者は「飾るべき」、若い世代は「飾りたくない」
- 配偶者は「飾りたい」、子供は「重荷に感じる」
- 長男は「義務」、次男以下は「自由にしたい」
解決策の提案:
時間を区切る方法
「最初の1年間は飾り、その後は相談する」など、期間を決めて始める方法です。
場所で折り合う方法
「リビングは避けて、寝室に小さく飾る」など、飾る場所を限定する方法です。
複数作成による分散
遺影を複数作成し、飾りたい家族のところにだけ置く方法です。写真館では、同じ写真から複数の遺影を作成できます。
交代制
月単位や季節単位で、飾る担当を交代する方法もあります。
最も大切なのは、それぞれの気持ちを尊重し、故人への思いを共有することです。完璧な解決策がなくても、家族で話し合う過程そのものが故人への供養になります。
まとめ
遺影専門写真館で15年間働いてきた経験から、「遺影を飾るのがよくない」という迷信について詳しく解説いたしました。結論として、遺影を飾ることに問題は一切なく、むしろ故人を偲ぶ素晴らしい方法の一つです。
よくないとされる理由の多くは科学的根拠のない迷信であり、本当に注意すべきは湿気や直射日光といった実用的な問題のみです。現代では住宅事情や価値観の変化により、従来通りに飾ることが困難な場合も多く、小さくリサイズしたりデジタル化したりする新しい供養方法も生まれています。
最も大切なのは、迷信に惑わされず正しい知識を持つこと、そして故人を偲ぶ気持ちを大切にすることです。飾る・飾らないの選択は完全に自由であり、ご家族の状況と気持ちに合わせて判断していただければと思います。
遺影に関するお悩みがございましたら、お近くの写真館にもお気軽にご相談ください。
▼ この記事を書いた人

えがお写真館にて、これまでに1000人以上のシニア世代の方々を撮影して来ました。
お客様は、今でも毎日運動し、本を読み、自分の事は自分で行い、人の手は決して借りないという、毎日を謳歌している魅力的なシニアの方ばかりでした。
今まで経験してきた事が表情や仕草に全て出て、魅力的な雰囲気を出しておりますので、そのお姿を毎回撮影させて頂いております。
お客様の優しいえがおを見ると、自然と私達も嬉しくなって同じえがおになっている事によく気づく事があります。皆さんのえがおが私達スタッフ皆んなの元気の源です!