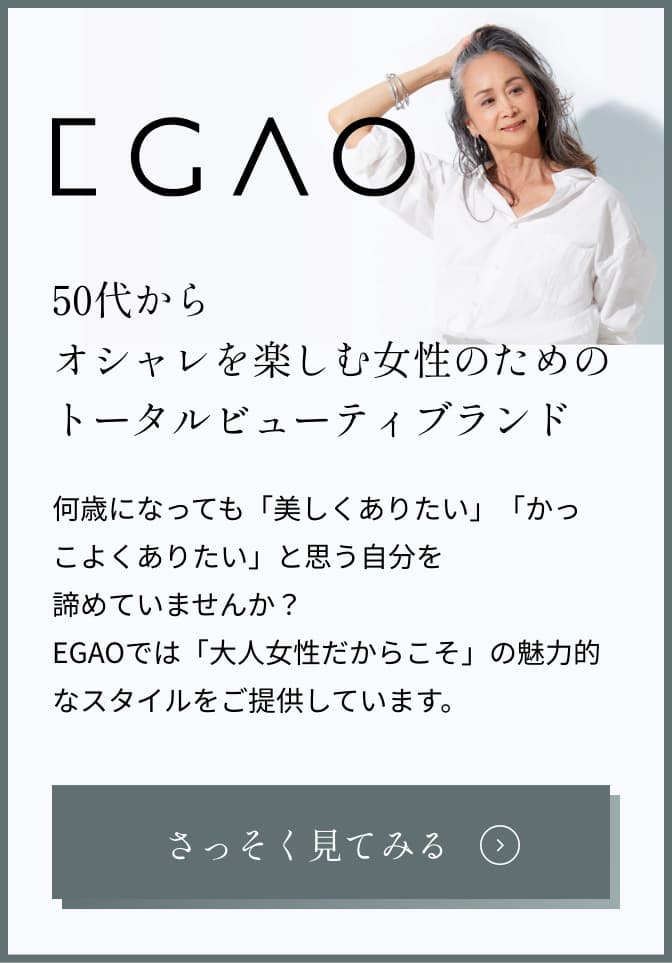ステキなヒント
遺影の読み方は「いえい」|遺影の基本知識と選び方
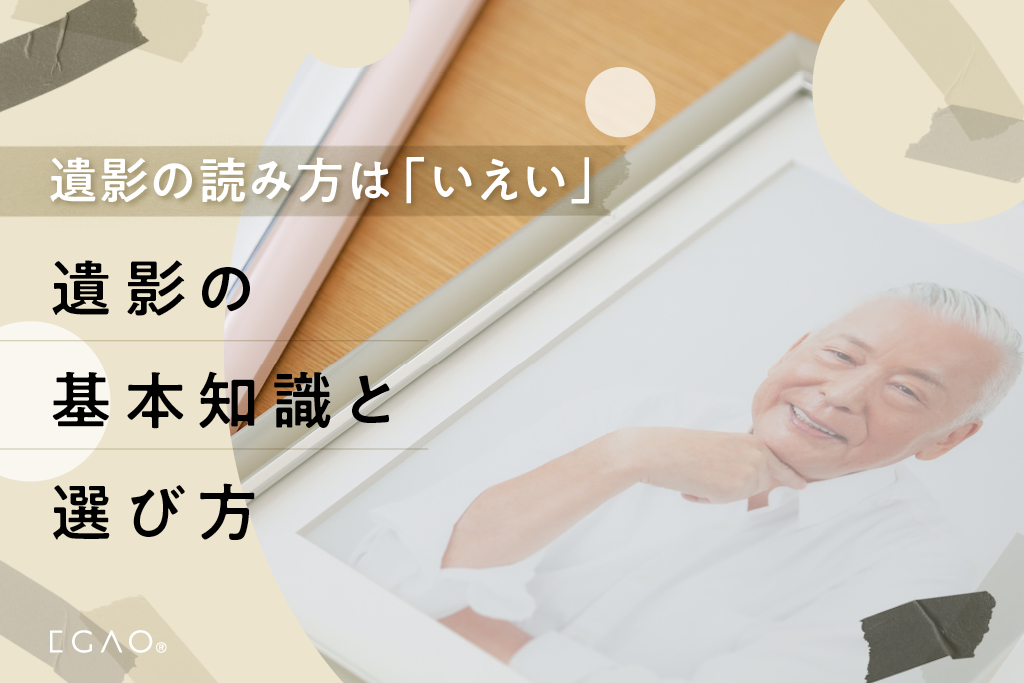
- 1. 1. 「遺影」の正しい読み方と基本知識
- 1.1. 1-1. 遺影は「いえい」と読みます
- 1.2. 1-2. お客様からよくある読み方の質問
- 1.3. 1-3. 遺影の意味と役割
- 2. 2. 写真館スタッフが教える遺影写真の基礎知識
- 2.1. 2-1. 遺影に適した写真の条件
- 2.2. 2-2. よくある写真選びの失敗例
- 2.3. 2-3. 加工でできることとできないこと
- 3. 3. 実務経験から学ぶ遺影写真の選び方
- 3.1. 3-1. 撮影時期の選び方のポイント
- 3.2. 3-2. 表情や角度の選び方
- 3.3. 3-3. 背景や服装の考慮点
- 4. 4. 遺影作成の流れと料金について
- 4.1. 4-1. 写真館での遺影作成の流れ
- 4.2. 4-2. 料金相場と作成期間
- 4.3. 4-3. 緊急時の対応方法
- 5. 5. 遺影に関するよくある質問と回答
- 5.1. 5-1. 生前撮影について
- 5.2. 5-2. デジタルデータでの保存
- 5.3. 5-3. 複数枚作成の必要性
- 6. まとめ
遺影専門写真館で長年働いている私たちスタッフが、日々お客様から最もよくいただくご質問があります。それは「遺影って、何て読むんですか?」というものです。
実際に、お電話でのお問い合わせの際に「いえい写真の件で…」と言われるお客様もいれば、「ゆいえい?」「いかげ?」と迷いながらお話しされる方も少なくありません。正しい読み方を知らないことは決して恥ずかしいことではありませんし、私たちスタッフも最初は戸惑った経験があります。
この記事では、遺影専門写真館のスタッフとして15年以上の経験を持つ私が、遺影の正しい読み方から、実際の写真選びで失敗しないためのポイントまで、現場で培った知識を余すことなくお伝えいたします。
1. 「遺影」の正しい読み方と基本知識

1-1. 遺影は「いえい」と読みます
「遺影」の正しい読み方は「いえい」です。これは間違いありません。
私たち写真館スタッフの経験では、初めてご相談にいらっしゃるお客様の約3割の方が、この読み方に不安を感じていらっしゃいます。特に電話でのお問い合わせの際は、「遺影写真について聞きたいのですが…えーっと、いえい、で合ってますでしょうか?」とご確認される方も多くいらっしゃいます。
漢字だけを見ると「ゆいえい」や「いかげ」と読んでしまいそうになりますが、正しくは「いえい」です。「遺」は「い」、「影」は「えい」と読みます。
1-2. お客様からよくある読み方の質問
写真館での接客で、お客様から実際にいただく読み方に関する質問をご紹介します。
よくある質問例:
- 「ゆいえいって読むんじゃないんですか?」
- 「いかげって聞いたことがあるんですが…」
- 「地域によって読み方が違うんでしょうか?」
これらの疑問は本当によくお聞きします。しかし、全国どこでも「いえい」が正しい読み方です。地域による違いはありません。
「遺」という漢字は、他の熟語では「遺産(いさん)」「遺書(いしょ)」のように「い」と読むことが多いため、「遺影」も「いえい」と読むのが自然なのです。
1-3. 遺影の意味と役割
遺影とは、故人を偲ぶために通夜や葬儀の祭壇に飾る故人の写真や肖像画のことです。
写真館での仕事を通じて感じるのは、遺影には単なる写真以上の深い意味があるということです。それは「故人との最後の対話の場」を提供する役割です。参列者の方々が遺影を見つめながら、故人への最後の言葉を心の中で語りかける。そんな大切な瞬間を支える写真なのです。
遺影に宗教的な意味はありません。仏教、神道、キリスト教、どの宗教でも、また無宗教の方でも、故人を偲ぶ気持ちがあれば遺影を飾ることができます。
2. 写真館スタッフが教える遺影写真の基礎知識
2-1. 遺影に適した写真の条件
15年以上の経験から、遺影に適した写真には明確な条件があることがわかってきました。
技術的な条件:
- 画素数: 最低200万画素以上(できれば300万画素以上)
- ピント: 顔がしっかりとピントが合っている
- 顔のサイズ: 写真の中で顔が10円玉大以上の大きさで写っている
- 明るさ: 顔が適度な明るさで写っている(暗すぎず、明るすぎず)
内容的な条件:
- 故人の人柄が伝わる自然な表情
- できるだけ1~5年以内に撮影されたもの
- カメラ目線であること(必須ではありませんが望ましい)
これらの条件を満たしていれば、スナップ写真でも十分に美しい遺影に仕上げることができます。
2-2. よくある写真選びの失敗例
写真館での経験で、お客様が陥りがちな写真選びの失敗例をご紹介します。これらを知っておくことで、同じような失敗を避けることができます。
失敗例1: 古すぎる写真を選んでしまう
「若い頃の一番綺麗な写真を使いたい」というお気持ちはよくわかります。しかし、20年以上前の写真を使うと、参列者の方が「どなたですか?」と困惑してしまうことがあります。故人を知る方々が「ああ、この方だ」とすぐに分かる年代の写真を選ぶことが大切です。
失敗例2: 証明写真を選んでしまう
免許証や履歴書用の証明写真は、確かにきちんとした印象を与えます。しかし、表情が硬すぎて故人の人柄が伝わりにくいことがあります。もう少し自然な表情の写真があれば、そちらを選ぶことをお勧めします。
失敗例3: 画質を確認せずに選んでしまう
スマートフォンで撮った写真でも、拡大してみると意外とピンボケしていることがあります。遺影は四つ切サイズ(約25cm×30cm)に引き伸ばすため、元の写真でピンボケしていると、仕上がりがぼやけた印象になってしまいます。
2-3. 加工でできることとできないこと
写真館では様々な加工技術を用いて、お客様の写真を最適な遺影に仕上げています。しかし、加工にも限界があります。
加工でできること:
- 背景の変更(無地の背景に変更)
- 服装の変更(スーツや着物への変更)
- 明るさ・コントラストの調整
- 軽微な肌の修正
- 髪型の微調整
- 不要な物の除去(眼鏡の映り込み、背景の人物など)
加工で難しいこと:
- 大幅なピンボケの修正
- 極端に暗い写真の修正
- 顔の向きの大幅な変更
- 表情の根本的な変更
- 年齢を大幅に若返らせること
お客様には「加工で何でもできます」とは申し上げません。元の写真の品質が仕上がりに大きく影響するため、できるだけ条件の良い写真をお選びいただくことが重要です。
3. 実務経験から学ぶ遺影写真の選び方
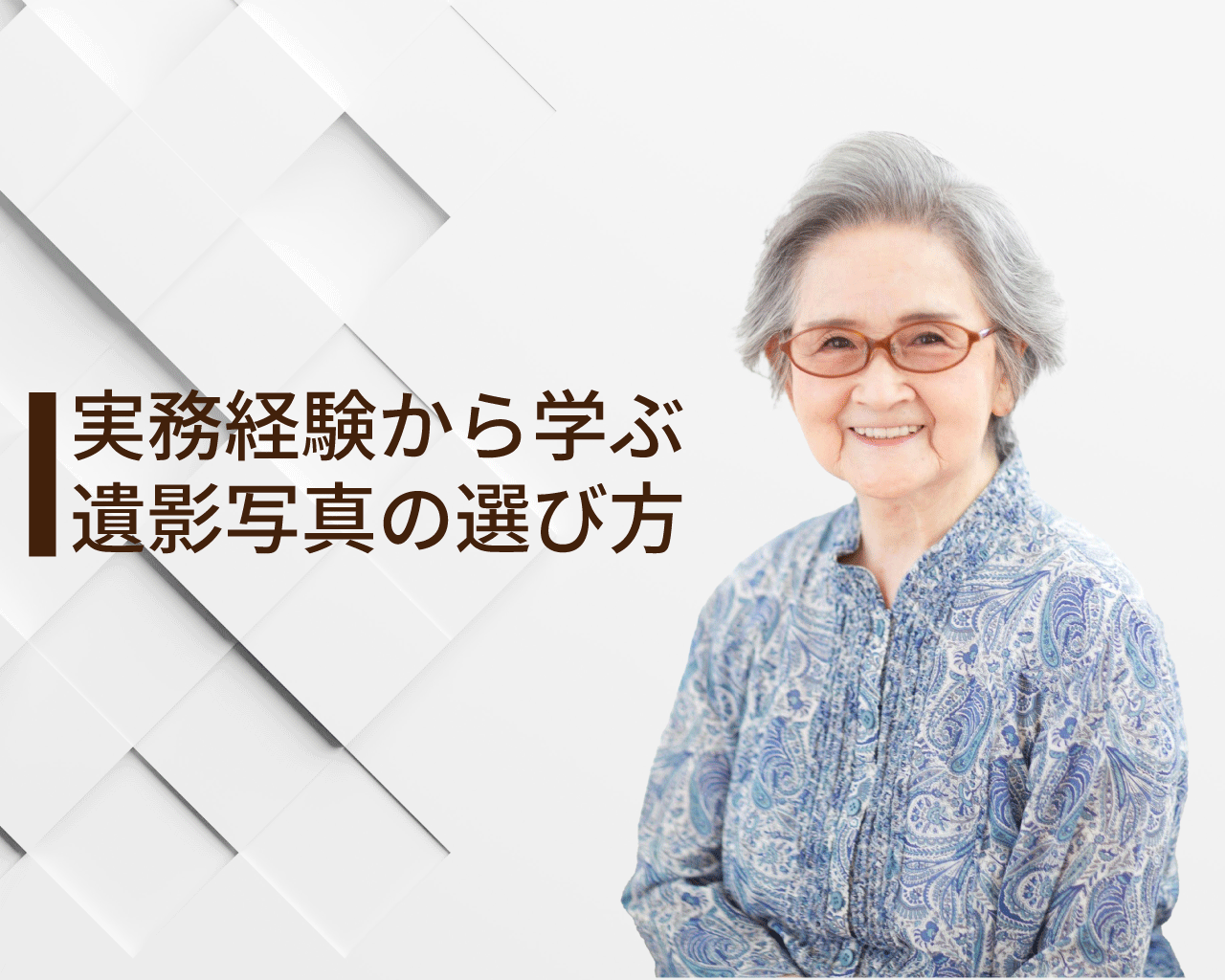
3-1. 撮影時期の選び方のポイント
遺影写真の撮影時期について、お客様からよくご相談をいただきます。実務経験から得た最適な撮影時期の選び方をお伝えします。
基本的な考え方:
一般的には「亡くなる1~5年以内」の写真が適していると言われています。しかし、私たちが重視するのは撮影時期よりも「参列者の方々が見て、すぐに故人だと分かる写真」であることです。
特別な状況での考え方:
- 長期間の闘病の場合: 病気になる前の元気な時期の写真を選ぶことをお勧めします
- 事故による急逝の場合: 直近1年以内でお元気だった頃の写真が理想的です
- 高齢での逝去の場合: 2~3年以内であれば、多少古くても問題ありません
実際の事例として、90歳で亡くなられた方のご遺族が「5年前の85歳の時の写真」を選ばれたケースがありました。この場合、5年前でも十分に「最近の故人」として認識していただけます。
3-2. 表情や角度の選び方
遺影写真の表情選びは、ご遺族の方にとって最も悩ましい部分かもしれません。写真館での経験を踏まえ、適切な表情選びのポイントをお伝えします。
理想的な表情:
- 自然な微笑み(作り笑いではない、心からの笑顔)
- 穏やかな表情(リラックスした状態)
- 優しい眼差し(見る人に安心感を与える)
避けた方が良い表情:
- 大笑いしている写真(葬儀の厳粛な雰囲気に合わない場合がある)
- 極端に真剣すぎる表情(親しみやすさに欠ける)
- うつむいた表情(参列者との「目線の交流」が生まれない)
角度について:
正面から撮影された写真が最も使いやすいのは確かです。しかし、少し斜めから撮影された写真でも、顔がしっかりと見える角度であれば問題ありません。横向きや後ろ向きの写真は、遺影には適していません。
3-3. 背景や服装の考慮点
写真を選ぶ際、背景や服装を気にされるご遺族の方が多くいらっしゃいます。しかし、現在の加工技術により、これらは後から調整可能です。
背景について:
- 旅行先での写真: 思い出の場所であれば、背景をそのまま活かすことも可能
- 自宅での写真: 生活感のある背景は、無地の背景に変更可能
- 集合写真から切り出し: 故人部分のみを抽出して遺影作成可能
服装について:
- 普段着の写真: フォーマルな服装に変更可能
- 作業着の写真: スーツや和装に変更可能
- 寝間着の写真: 適切な服装に変更可能
実際の事例として、お孫さんと一緒に撮った普段着の写真から、背景を上品な色合いに変更し、服装を黒のスーツに変更して、とても素敵な遺影に仕上げたケースがあります。元の写真の「おじいちゃんらしい優しい笑顔」はそのまま活かしながら、葬儀にふさわしい仕上がりにすることができました。
4. 遺影作成の流れと料金について
4-1. 写真館での遺影作成の流れ
写真館での遺影作成の実際の流れをご紹介します。この流れを知っておくことで、スムーズに遺影を準備することができます。
Step 1: ご相談・写真選び(30分~1時間)
- お客様のご希望をお聞きします
- お持ちいただいた写真の中から最適なものを一緒に選びます
- 加工内容について詳しくご説明します
- 仕上がり予定日をお伝えします
Step 2: 写真のデジタル化・加工(2~3時間)
- 現物写真の場合は高解像度でスキャニング
- 背景・服装の変更作業
- 明るさ・コントラストの最適化
- 品質チェック
Step 3: プリント・額装(1~2時間)
- 高品質な写真用紙へのプリント
- 額縁への装着
- リボンや装飾の取り付け
- 最終品質チェック
Step 4: お引き渡し
- 仕上がりをご確認いただきます
- 取り扱い方法をご説明します
- アフターサービスについてご案内します
4-2. 料金相場と作成期間
写真館での遺影作成料金は、以下のような構成になっています。
基本料金の内訳:
- 写真加工費: 8,000円~15,000円
- プリント費: 3,000円~5,000円
- 額縁費: 5,000円~20,000円
- 合計: 16,000円~40,000円
作成期間:
- 通常: 2~3日
- 急ぎの場合: 当日~翌日(追加料金が発生)
- 特殊加工が必要な場合: 3~5日
料金は加工の複雑さや額縁のグレードによって変わります。基本的な背景変更と服装変更であれば、20,000円~25,000円程度が相場です。
4-3. 緊急時の対応方法
急なご不幸で、翌日までに遺影が必要な場合の対応方法をご説明します。
緊急対応のポイント:
- 電話で事前に状況をお伝えください
- 写真は複数枚お持ちいただくと選択肢が広がります
- 額縁は在庫のあるものから選んでいただきます
- 追加料金(5,000円~10,000円)が発生します
緊急時でも品質は維持します:
時間が限られていても、写真館としての品質基準は下げません。ただし、通常よりも作業時間が制限されるため、複雑な加工は難しい場合があります。
私たちの経験では、前日の夕方にご依頼いただき、翌朝の通夜に間に合わせたケースも数多くあります。緊急の場合でも、まずはお電話でご相談ください。
5. 遺影に関するよくある質問と回答
5-1. 生前撮影について
Q: 生前に遺影を撮影するのは縁起が悪いのでしょうか?
A: 全くそのようなことはありません。むしろ、最近は生前に遺影を準備される方が増えています。
写真館での経験では、生前撮影をされる方は年々増加しており、現在では全体の約20%の方が生前に遺影を準備されています。生前撮影の最大のメリットは、ご本人が納得のいく写真を時間をかけて撮影できることです。
生前撮影のメリット:
- ご本人の希望を反映できる
- 体調の良い時に撮影できる
- 家族の負担を軽減できる
- 時間をかけて最適な一枚を選べる
Q: 生前撮影の場合、どのような服装が良いでしょうか?
A: フォーマルな服装が基本ですが、故人らしさを表現できる服装も喜ばれます。
男性の場合は濃紺やグレーのスーツ、女性の場合は落ち着いた色のワンピースや着物が人気です。ただし、故人が普段からカジュアルな服装を好まれていた場合は、上品なカジュアル服装でも問題ありません。
5-2. デジタルデータでの保存
Q: 遺影写真のデジタルデータはもらえますか?
A: はい、基本的にはデジタルデータもお渡ししています。
多くの写真館では、作成した遺影のデジタルデータをCD-RやUSBメモリーでお渡ししています。これにより、法事の際に追加プリントが必要な場合や、小さなサイズの写真が必要な場合に対応できます。
デジタルデータの活用例:
- 法事用の小サイズプリント
- 家族や親戚への配布用
- 新聞の訃報記事用
- Web上の追悼サイト用
Q: スマートフォンで撮影した写真でも遺影になりますか?
A: はい、条件が整っていれば十分に美しい遺影になります。
最近のスマートフォンのカメラ性能は非常に高く、適切な条件で撮影されていれば、専用のカメラで撮影した写真と遜色ない遺影を作成できます。重要なのは画素数やピントよりも、「故人らしい表情が捉えられているか」です。
5-3. 複数枚作成の必要性
Q: 遺影は何枚作成すれば良いでしょうか?
A: 一般的には2~3枚作成される方が多いです。
標準的な枚数配分:
- 葬儀用(大きなサイズ): 1枚
- 自宅用(中サイズ): 1枚
- 予備・親戚配布用(小サイズ): 1~2枚
Q: サイズは何種類作れますか?
A: 写真館では様々なサイズに対応しています。
一般的なサイズ:
- 四つ切(25.4cm × 30.5cm): 葬儀の祭壇用
- A4(21.0cm × 29.7cm): 自宅の仏壇周辺用
- 2L(12.7cm × 17.8cm): コンパクトな自宅用
- L(8.9cm × 12.7cm): 携帯用・配布用
同じ写真から複数のサイズを作成する場合は、2枚目以降は割引価格でご提供している写真館が多いです。
まとめ
遺影専門写真館のスタッフとして長年お客様と接する中で、遺影に対する理解や準備方法は時代とともに変化してきました。しかし、変わらないのは「故人を偲ぶ気持ち」と「最後のお別れを大切にしたい」という想いです。
「遺影」の読み方は「いえい」です。この基本的な知識から始まり、写真選びのポイント、加工の可能性、そして実際の作成プロセスまで、現場での経験を踏まえてお伝えしました。
最も重要なことは、技術的な条件よりも「故人らしさが伝わる写真」を選ぶことです。完璧な写真である必要はありません。家族の思い出に残る、故人の人柄が感じられる一枚があれば、私たち写真館スタッフが最大限に活かして、美しい遺影に仕上げます。
生前撮影も含め、遺影について不安や疑問がございましたら、お気軽に最寄りの写真館にご相談ください。私たちは、故人との最後の対話の場となる大切な遺影作りを、責任を持ってサポートいたします。
▼ この記事を書いた人

えがお写真館にて、これまでに1000人以上のシニア世代の方々を撮影して来ました。
お客様は、今でも毎日運動し、本を読み、自分の事は自分で行い、人の手は決して借りないという、毎日を謳歌している魅力的なシニアの方ばかりでした。
今まで経験してきた事が表情や仕草に全て出て、魅力的な雰囲気を出しておりますので、そのお姿を毎回撮影させて頂いております。
お客様の優しいえがおを見ると、自然と私達も嬉しくなって同じえがおになっている事によく気づく事があります。皆さんのえがおが私達スタッフ皆んなの元気の源です!