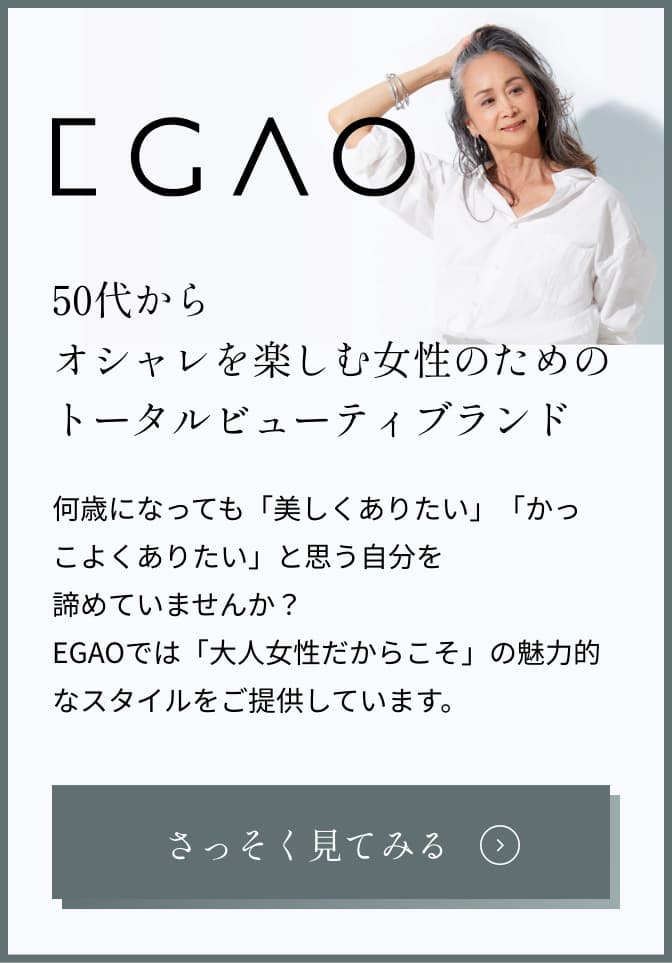ステキなヒント
遺影サイズの選び方を解説|遺影撮影写真館が教える最新情報

- 1. 遺影サイズの基本|用途別サイズ一覧表
- 1.1. 祭壇用サイズ(四つ切・A4)の特徴と選び方
- 1.2. 焼香台・仏壇用サイズ(L判・キャビネ・2L)の使い分け
- 1.3. 持ち歩き用・メモリアル用の小サイズ展開
- 2. 写真館が教える画質とサイズの関係
- 2.1. サイズ別に必要な画素数の目安
- 2.2. 引き伸ばし時の画質劣化を防ぐコツ
- 2.3. スマホ写真でも美しい遺影にする方法
- 3. 生前撮影で選ぶべき最適サイズ
- 3.1. 将来の用途を考えたサイズ選び
- 3.2. 複数サイズ同時作成のメリット
- 3.3. データ保存と後日サイズ変更の可能性
- 4. 遺影サイズ選びでよくある失敗例と対策
- 4.1. 緊急時に困らない事前準備のポイント
- 4.2. 額縁サイズとのミスマッチを避ける方法
- 4.3. 加工・修正時のサイズ変更注意点
- 5. プロが教える遺影写真の選び方
- 5.1. サイズ以外で重要な写真選びの条件
- 5.2. 表情・構図・服装の基本ポイント
- 5.3. 写真館での生前撮影のメリット
- 6. まとめ
遺影撮影専門の写真館フォトグラファーとして、これまで数多くのお客様の遺影撮影をお手伝いしてきました。近年、生前に遺影を準備される方が急激に増えており、2025年に入ってからは前年比で約40%も増加しています。
しかし、実際の撮影現場でよく耳にするのが「どのサイズで撮影すればいいの?」という疑問です。適切でないサイズを選んでしまい、いざという時に使えなかった、画質が粗くなってしまったという失敗例を数多く見てきました。
この記事では、遺影撮影専門フォトグラファーの経験をもとに、用途に応じた最適なサイズ選びから、将来を見据えた準備方法まで詳しく解説いたします。大切な方への思いを込めた一枚を、最適な形で残すためのガイドとしてお役立てください。
遺影サイズの基本|用途別サイズ一覧表
遺影写真には明確な「決まり」はありませんが、使用する場面に応じて適切なサイズが存在します。まずは、基本となるサイズと用途を整理してご説明いたします。
祭壇用サイズ(四つ切・A4)の特徴と選び方
四つ切サイズ(254mm×305mm)
葬儀の祭壇で最も多く使用される標準的なサイズです。参列者が離れた場所からでも故人のお顔をはっきりと確認できる大きさで、格式のある印象を与えます。
写真館での撮影経験から申し上げると、四つ切サイズは最も汎用性が高く、どのような葬儀スタイルにも対応できる安心のサイズです。出棺の際にご遺族が胸に抱かれる写真としても、適度な重厚感があり、お別れの儀式にふさわしい存在感を持ちます。
A4サイズ(210mm×297mm)
四つ切よりもやや縦長の形状で、モダンな祭壇や家族葬などでよく選ばれています。コンパクトでありながら、故人のお顔は十分に大きく表示され、実用性と美しさを兼ね備えたサイズです。
近年の傾向として、従来の格式張った葬儀よりも、故人らしさを大切にする葬儀スタイルが増えており、A4サイズの需要も高まっています。
焼香台・仏壇用サイズ(L判・キャビネ・2L)の使い分け
L判サイズ(89mm×127mm)
焼香台や仏壇でよく使用される小サイズです。葬儀後、ご自宅の仏壇周りに長期間お飾りいただくのに最適な大きさで、日常の中で故人を身近に感じられるサイズです。
キャビネサイズ(100mm×145mm)
L判よりもひと回り大きく、仏壇が大きめのご家庭や、リビングなどに単独でお飾りする場合に適しています。遠方の親族が写真をお持ち帰りになる際にも、見やすい適度なサイズとして喜ばれます。
2Lサイズ(127mm×178mm)
小サイズの中では最も大きく、焼香台で故人のお顔をしっかりと印象づけたい場合や、自宅での法要時により存在感を持たせたい場合に選ばれています。
持ち歩き用・メモリアル用の小サイズ展開
近年増えているのが、お財布に入れて持ち歩ける「カードサイズ」や「名刺サイズ」の遺影です。故人をいつも身近に感じていたいというご家族の想いから生まれたサイズで、特に若い世代の方からのご要望が多くなっています。
また、複数のお写真を組み合わせた「メモリアルフレーム」用として、小さなサイズを複数枚作成されるケースも増加傾向にあります。
写真館が教える画質とサイズの関係
遺影写真において、サイズと画質は密接に関係しています。適切でない画質の写真を大きなサイズに引き伸ばすと、参列者に不快な印象を与えてしまう恐れがあります。
サイズ別に必要な画素数の目安
四つ切・A4サイズの場合
最低でも300万画素、推奨は500万画素以上の写真をお勧めしています。これは印刷時の解像度300dpiを確保するために必要な数値です。現在のスマートフォンであれば、ほとんどの機種でこの条件をクリアしています。
L判・キャビネサイズの場合
200万画素以上で十分ですが、将来的に大きなサイズに変更する可能性を考慮すると、やはり500万画素以上で撮影しておくことをお勧めします。
撮影現場でよく遭遇するのが、古いガラケーで撮影された写真や、SNSにアップロードして画質が劣化した写真を元にしようとするケースです。このような写真は、どんなに表情が良くても、大きなサイズでは使用が困難になります。
引き伸ばし時の画質劣化を防ぐコツ
写真を引き伸ばす際の画質劣化を最小限に抑えるポイントをご紹介します。
撮影時の注意点
まず、撮影時にはできるだけ高解像度で撮影することが基本です。また、手ブレを避けるため、三脚の使用や、スマートフォンの場合はタイマー機能を活用することをお勧めします。
保存形式の選択
JPEGファイルは圧縮により画質が劣化します。可能であればRAW形式や、最高画質のJPEG設定で保存してください。また、写真を何度も編集・保存すると画質が低下するため、元の写真は必ずバックアップを取ってから加工作業を行ってください。
プロの加工技術
当写真館では、AI技術を活用した画質向上処理も行っております。多少解像度が不足している写真でも、専門的な処理により美しい遺影に仕上げることが可能です。
スマホ写真でも美しい遺影にする方法
現代では、最も身近な写真の多くがスマートフォンで撮影されています。スマートフォンの写真でも、適切な準備をすれば美しい遺影を作成できます。
撮影時のポイント
自然光が入る窓際での撮影がベストです。人工照明だけでは、顔に影ができやすく、遺影として不適切な仕上がりになる場合があります。また、少し上から撮影することで、より美しい表情を捉えることができます。
写真選びのコツ
複数枚撮影した中から、目にピントがしっかりと合っているもの、表情が自然で明るいものを選んでください。拡大して確認し、ブレやボケがないかをチェックすることも重要です。
生前撮影で選ぶべき最適サイズ
生前に遺影を準備される場合、将来のあらゆる用途を想定したサイズ選びが重要になります。
将来の用途を考えたサイズ選び
生前撮影の最大のメリットは、時間をかけて最適な写真を準備できることです。しかし、将来どのような葬儀スタイルになるか、どのような用途で使用するかは予測が困難です。
そこで当写真館では、「フルサイズでの撮影・データ保存」をお勧めしています。高解像度の元データがあれば、将来どのようなサイズにも対応できるからです。
推奨する準備パターン

- 四つ切サイズ 1枚(葬儀用メイン)
- L判サイズ 2〜3枚(仏壇用・配布用)
- 元データの保存(将来の追加作成用)
このパターンであれば、一般的な葬儀から家族葬まで、どのようなスタイルにも対応できます。
複数サイズ同時作成のメリット
生前撮影では、一度の撮影で複数サイズを同時作成することで、コストを抑えながら万全の準備ができます。
経済的メリット
後から追加でサイズ変更や焼き増しをするよりも、同時作成の方が1枚あたりの単価を抑えることができます。また、緊急時に急いで追加作成する必要がないため、精神的な負担も軽減されます。
品質の統一
同じ撮影セッションで作成された写真は、色調や明るさが統一されており、どのサイズでも同じ美しい仕上がりを得ることができます。
データ保存と後日サイズ変更の可能性
デジタル時代の大きなメリットは、元データを保存しておけば、後日いくらでもサイズ変更や追加作成が可能なことです。
データ保存の重要性
当写真館では、撮影した写真の高解像度データをCD-Rまたはクラウドストレージでお渡ししています。このデータがあれば、10年後、20年後でも同じ品質での追加作成が可能です。
将来のニーズに対応
法要の際の追加写真、親族への配布用、海外に住む家族への郵送用など、予期せぬニーズが発生することもあります。元データがあれば、いつでも迅速に対応できます。
遺影サイズ選びでよくある失敗例と対策
長年の撮影経験の中で、多くの失敗例を見てきました。これらの経験を共有することで、同じ失敗を避けていただけるよう、具体例とともに対策をご紹介します。
緊急時に困らない事前準備のポイント
失敗例1:サイズが合わない
「急な葬儀で慌てて写真を探したが、手元にあるのは小さなL判のみ。祭壇用の大きなサイズがなく、引き伸ばしたら画質が粗くなってしまった。」
このような失敗を避けるためには、生前に最低でも四つ切サイズの遺影を1枚準備しておくことをお勧めします。大きなサイズから小さなサイズへの変更は容易ですが、その逆は困難だからです。
失敗例2:写真が見つからない
「いい写真があったはずだが、大量の写真の中から探し出せない。時間がないため、納得できない写真で妥協することになった。」
写真の整理と保存場所の明確化が重要です。当写真館では、生前撮影の際に「遺影用」と明記したファイルでデータをお渡しし、ご家族にも保存場所をお知らせいただくようお願いしています。
額縁サイズとのミスマッチを避ける方法
失敗例3:額縁に合わない
「用意してあった額縁と写真のサイズが合わず、急遽額縁を購入し直すことになった。葬儀当日の朝まで準備に追われた。」
額縁と写真のサイズは必ずセットで考える必要があります。特に注意が必要なのは、額縁の「内寸」と写真サイズの関係です。
対策のポイント
- 額縁購入時には必ず「内寸」を確認する
- 写真と額縁を同時に準備する
- マット(台紙)の有無による差も考慮する
当写真館では、遺影撮影の際に適切な額縁もご紹介しており、サイズミスマッチのトラブルを未然に防いでいます。
加工・修正時のサイズ変更注意点
失敗例4:加工後の画質劣化
「表情は気に入っているが背景に問題があるため加工を依頼。背景は美しくなったが、顔の部分がぼやけてしまった。」
写真の加工や修正を行う際は、元の写真の解像度が十分でないと、加工後に画質が劣化してしまいます。
専門業者選びのポイント
- 遺影専門の加工経験があるか確認する
- 元写真の画質チェックを事前に行ってくれるか
- 加工前後での画質保証があるか
プロが教える遺影写真の選び方
サイズ以外にも、美しい遺影を作成するために重要なポイントがあります。撮影現場での経験をもとに、実践的なアドバイスをお伝えします。
サイズ以外で重要な写真選びの条件
ピントの確認
まず確認すべきは、目にしっかりとピントが合っているかどうかです。遺影では、故人の目に参列者の視線が集まるため、ここがぼけていると全体の印象が大きく損なわれます。
明るさと色調
暗すぎる写真や、色調が偏っている写真は避けてください。遺影では、顔全体が明るく、自然な色合いで写っていることが重要です。逆光で撮影された写真や、蛍光灯の下で緑がかって写った写真などは、加工で修正可能ですが、元の写真が自然な条件で撮影されていることがベストです。
表情の自然さ
以前は格式張った真剣な表情が好まれていましたが、現在では自然で温かみのある表情が選ばれる傾向にあります。故人らしさが感じられる、穏やかで親しみやすい表情の写真を選ぶことをお勧めします。
表情・構図・服装の基本ポイント
表情について
微笑みを浮かべた写真が最近のトレンドですが、重要なのは「故人らしさ」です。普段よく笑う方であれば笑顔の写真を、落ち着いた方であれば穏やかな表情の写真を選ぶことで、参列者が「その人らしい」と感じられる遺影になります。
構図のポイント
胸から上が写った「バストアップ」の構図が最も一般的で、遺影として適しています。全身が写った写真や、顔が小さすぎる写真は、拡大時に不自然になる可能性があります。
また、カメラ目線の写真が基本ですが、少し斜めを向いた写真でも、目がこちらを向いていれば問題ありません。
服装の考え方
以前は黒や紺などの地味な色が好まれていましたが、現在では故人が好んでいた色や、その人らしい服装での遺影も多く見られます。
ただし、あまりに派手すぎる色や柄は避け、清潔感のある服装を選ぶことが大切です。背景の加工や服装の修正も可能ですので、表情や全体の雰囲気を優先して選んでください。
写真館での生前撮影のメリット
最後に、生前撮影専門の写真館を利用するメリットについてお伝えします。
技術的なメリット
プロの照明機材を使用することで、どのような肌質の方でも美しく撮影できます。また、遺影に特化した撮影技術により、後から加工を行わなくても、そのまま使用できる品質の写真を撮影できます。
心理的なサポート
生前撮影は、多くの方にとって特別な体験です。当写真館では、リラックスして撮影に臨んでいただけるよう、十分な時間をかけてカウンセリングを行い、お客様のご要望を丁寧にお聞きしています。
アフターサービス
撮影後も、データの保管や追加作成、修正作業など、長期にわたってサポートいたします。また、ご家族からのご相談にも対応し、最適な形で遺影をご準備いただけるようお手伝いしています。
まとめ

遺影のサイズ選びは、用途に応じた適切な判断が重要です。祭壇用には四つ切またはA4サイズ、仏壇用にはL判からキャビネサイズが基本となりますが、最も大切なのは故人らしさが表現された美しい写真を準備することです。
生前撮影の場合は、高解像度での撮影と複数サイズでの準備により、将来のあらゆるニーズに対応できます。画質確保のためには最低300万画素以上、推奨500万画素以上の写真を選び、ピントと明るさを重視してください。
緊急時に慌てることがないよう、今から準備を始めることをお勧めします。
▼ この記事を書いた人

池田 基 (いけだ もとい)
えがお写真館 フォトグラファー
【“えがお”がある場所】
撮り終えた写真を見て、安心した表情、嬉しい表情を見ることが私の喜びになっています。撮影の雰囲気は慣れていないとそれだけで緊張してしまいます。それでなくても、1人で写真撮影をするということは緊張します。
そんな撮影雰囲気を出さず、笑いのある場所であれば緊張せず撮影できます。
そんな場所にしています。
ヘアメイクで綺麗になり、安心して撮影が出来る場所だと思っています。
帰りの方がイキイキとえがおになる場所だと思っています。